いじめ、子どものメンタル、学校風土…学校に関わる研究所の社会実装のご案内
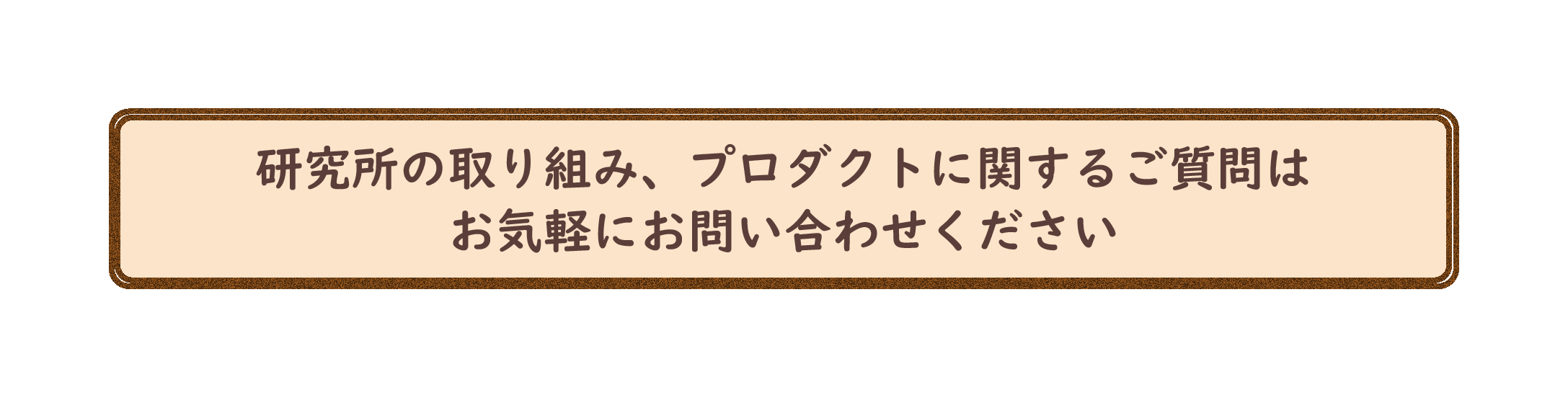
|
|
いじめ予防への取り組み |
いじめは教育現場のみならず日本社会において大きな問題です。しかし、様々な取り組みにも関わらず、改善された様子が見られません。
一方、世界では、いじめについての研究が日々進んでいます。
子どもの発達科学研究所は、そうした最先端の研究成果に加え、弊所が実際に調査した結果を基に、学校現場で包括的に取り組むことができるプログラムを提供し続けています。
| 主な取り組み |
-
- ● いじめ予防プログラム「TRIPLE-CHANGE」
- ● TRIPLE-CHANGE 講座
- ● やはたポスター
- ● いじめ予防動画コンテンツ
- ● いじめ予防リーダー研修
- ● 自治体の実践例(吹田市) ※実践の様子をPDFで公開しています
- ● 学校風土いじめ調査
|
|
子どものメンタルヘルスを把握 |
こころの健康観察 NiCoLi
子どものこころの健康(抑うつ・不安)を定期的に観察して支援ニーズのある子どもを早期発見、早期支援体制の構築をすることによって、不登校やメンタルヘルスのさらなる悪化を予防することを目的としています。
2020年度から2年連続で、東海地方の中核都市の市内全小中学生(約6万人)を対象に実施しています。

ACE研究・啓発
こうした傷つき体験(ACE)が、成人期の社会的問題(引きこもり、不就労、貧困)、精神的健康問題(うつ、自殺、依存など)、身体的健康問題(生活習慣病、がん、心臓疾患)などに大きな影響を与えていることが、1990年代後半のアメリカにおける研究で明らかになり、大きな衝撃を与えました。
その後、ACEについて、世界中で研究が進められ、いじめ被害や教師からの強い叱責など、学校での傷つき体験、移民、災害被害なども、同様に成人期に悪影響を及ぼすことが分かってきており、それらの知見を社会に広め、子育てや教育支援に活かすことが大切だとされています。
弊所では、日本ではまだ十分に知られていないACE研究の結果を日本の皆様にも広く知っていただき、小児期の大切さを共有させていただくと共に、我が国においてほとんどされていないACE研究を進めたり、そこで分かったことをいち早く皆様にお届けできるように啓発、プログラム開発などを行っています。
|
|
学校風土改善への取り組み |
学校風土いじめ調査(子どものための学校調査)
「学校風土いじめ調査」は、学校で起こっている「いじめ」と、その学校や学級の「風土(雰囲気)」に着目した調査です。子どもたち一人一人へ無記名のアンケート調査(紙またはWeb)を行い、子どもたちの視点で「学校」「学級」の風土(雰囲気)を数値化します。
各々の教師が漠然と感じていた「学校」「学級」の『強み』や『弱み』をデータとして捉えることができ、教師間で共有できるようになります。
この調査結果から、エビデンスに基づいた具体的な学級経営が可能となります。
|
|
不登校・引きこもりへの取り組み |
不登校や引きこもり件数が増加し、社会問題となっています。その原因や対応方法に、科学的な視点からアプローチするセミナーを開催しています。
| 開催セミナー |
|
|
動画配信 「不登校を科学する」 講師:和久田学(公益社団法人子どもの発達科学研究所 主席研究員) |
|
|
研究所のご紹介 |
当研究所は、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学の5大学からなる「子どものこころの発達研究センター」で研究開発されたカリキュラムや教材、情報などを、ご両親やお子様たちが活用できるように、研究事業とその成果の普及支援をするために設立されました。
2010年に一般社団法人としてスタートし、2013年に公益社団法人へと移行しました。
子どもの発達、環境(家庭・学校)、就労まで、支援者支援というスタンスで研究と社会実装を行っています。また多くの民間企業と社会事業としてサスティナブルに、子ども、発達障害者への支援を行っています。
|
|
研究紹介 |
いじめ問題、子どもの発達、メンタルヘルスなどに関する様々な研究を行っています。
浜松医科大学や弘前大学をはじめとする各大学との共同研究等も実施しています。
主な研究
- ● 和久田学:子どもの問題行動の危険因子と保護因子の探求、いじめ予防の具体的方法、脳科学的見地からの学習支援、学校風土
- ● 大須賀優子:日本いじめ尺度の開発、学校風土尺度の開発、学校風土と子どもの行動の関連、脳科学的見地からの学習支援
- ● 西村倫子:学校風土尺度の開発、日本いじめ尺度の開発、子どもの情動行動に関する関連因子の探索、乳幼児期からの神経発達
研究員紹介




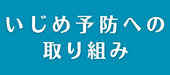
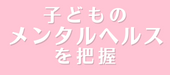
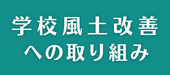
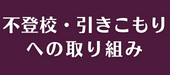
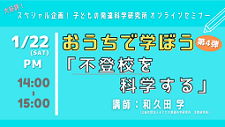
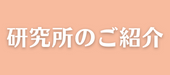

![またはお近くの研究所へ [本部] Tel 06-6341-5545 / [浜松] Tel 053-456-057](https://kodomolove.org/wp/wp-content/themes/twentythirteen_child/common/images/pages/txt_contact01.gif)